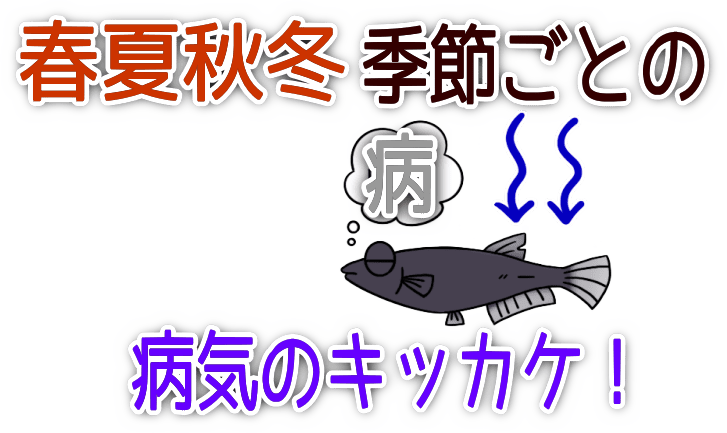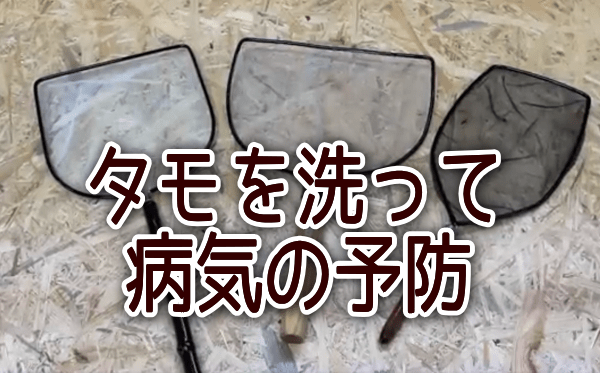塩水浴の効果と方法について(熱帯魚・金魚・メダカ共通)
【PR】※こちらの記事はamazonアソシエイトリンクを使用しています
魚には大きく分けて2つのタイプがいる
水を飲む必要がない魚と水を飲まないと干からびてしまう魚です。
浸透圧調整

魚たちは皆、浸透圧を調節しながら水中で生活しています。
濃度の低い方から濃度の高い方に水が移動していく力・水を引っ張る力を浸透圧と言います。
例えばキュウリの糠漬けです。
キュウリは90%以上が水分ですが、ぬか漬けにすることで、周りがぬかと塩に囲まれたことにより浸透圧の作用が働き、塩分はキュウリへ、水分は外へと移動していきます。
魚たちも、こうした浸透圧の影響を受けています。.png)
生物の塩分濃度
一般的に生き物の塩分濃度は0.9%ほどです。
.png)
ただ、彼らが住む川や湖の水に含まれる塩分濃度は0.05%以下とほぼ真水です。
淡水魚の場合
.png)
塩分をほぼ含まない淡水にすむ魚の場合、自分の周りの水よりも体液の塩分濃度が高くなります。
水は濃度の高いところへ移動する性質があるため淡水魚は水を飲まなくとも、水分が常に細胞に侵入していきます。
※淡水魚たちは水を飲む必要がありません。.png)
むしろ、そのまま水分が入り続けると細胞が破裂するため、尿などで沢山の水分を捨てていく必要があります。
侵入してきた水分を尿として放出することで体内の塩分濃度を保ちながら生きています。
海水魚の場合
.png)
海水魚の体液濃度も淡水魚同様に約0.9%前後です。
対して彼らが生息する海水中の塩分濃度は約3.5%と非常に高いです。.png)
体液よりも海水の方が塩分濃度が高いため、何もしなくても体の外に水分がどんどん出ていきます。
.png)
このままでは浸透圧により体内の水分が外に出て干からびてしまいます。
そのため、海水魚は海水をグイグイと飲み続けています。
海水魚は飲み込んだ海水の水分を吸収し海水の塩分だけを尿や主にエラから排出させるという特別な機能を備えています。
これによって体液濃度を保っています。
魚のお刺身がしょっぱくないのは海水魚たちが体内の塩分濃度を淡水魚同様(約0.9%)に保っているためとも言えます。
淡水でも海水でも生きられるメダカの不思議
.jpg)
多くの魚は浸透圧調整の機能として、いずれか一方の機能しかもっていないため、淡水魚は海水に棲むことができず、淡水魚もまた海水に棲むことはできません。
ただ、一部にはサケやウナギなどの川と海を行き来する魚がいます。
こういった一部の魚においては淡水魚と海水魚が持つこの両方の機能を持っており、環境に応じて器用に切り替え海水でも淡水でも生活することができます。.jpeg)
実はこうした機能が淡水にしか住んでいないメダカにも備わっていると言われています。
メダカたちは海水と淡水が交じり合う汽水域においても繁殖が可能であったり、また時間をかけ徐々に塩分濃度を高めていけば、完全な海水にも順応できると言われています。
※実際に行われた実験においても約50日程度で完全な海水に対応できるようになったそうです。
塩水浴を行う意味(効果)
観賞魚の世界・アクアリウムの世界には塩浴・塩水浴というものがあります。
主に淡水魚の病気の予防や治療として行われるものです。
ここまで読み進めていただいた内容が理解できていれば、塩水浴を行う意味も何となく理解できるかと思います。.png)
淡水魚たちは本来、必要のない水分まで体内に常時入ってきています。
そのまま入れっぱなしだと死んでしまうので、必死に尿などから水分を排出させています。
この作業は通常、健康な魚であれば自然に行われています。
ただ、病気や体調不良によって魚たちが弱っている場合、この作業自体によって更に体力が消耗してしまう可能性があります。
体調不良時の浸透圧調節は魚たちの負担となり上手く浸透圧調節が出来なくなることもあります。
飼育水の塩分濃度を魚たちの体内の塩分濃度に近づけることで水分が入ってくる量が少なくなります。
尿によって水分を排出するという作業が緩和され、排出負担が減少し、魚が楽になると言われています。
病気で治療中の弱った魚の体力回復にもつながると考えられています。
主な塩水浴の効果
- 魚たちの浸透圧調整による消耗が抑えられ体力の温存につながる
- 塩浴によって魚たちにとって不足しがちなミネラルの補給につながる
- 細菌などの弱体化や新たな増殖を抑えるなどの殺菌効果が期待できる
塩類細胞
他にも、塩類細胞と呼ばれる魚類の鰓などに分布する細胞があります。
これらはナトリウムやカリウムなど体の外へ排出させるような細胞です。
体の表面の入れ替わりの代謝が高まります。
この時に感染細胞や寄生虫も脱落すると言われています。
塩は病原体の増殖を抑えると言われていますが、効果は非常に薄く、塩だけで殺菌するのは難しいです。
塩で菌を殺す濃度というのは淡水魚が死んでしまう濃度になります。
治療に最適な塩分濃度は?
.png)
通常、塩水浴は0.3%から0.8%の間で行われます。
実際に入れる塩の量で言えば1ℓ当たり、0.3%であれば3グラム。
0.5%であれば5グラムの塩を加えます。
前述でお伝えした通り、淡水魚の体内の塩分濃度は約0.9%です。
0.9%を超えると多くの淡水魚の体内の塩分濃度を超えてしまいます。
最悪の場合、魚たちが脱水症状になる可能性もあります。
このような事情もあり、塩水浴は0.5%前後で行われることが多いです。
病気の治療として塩水浴を行う利点は浸透圧調整を楽にする以外にもあります。
例えば細菌や原生動物(げんせいどうぶつ)の体内の塩分濃度は0.35%程度と考えられています。.png)
仮に0.5%程度で塩浴することで細菌などの体内の塩分濃度よりも高い濃度のため細菌の増殖を抑えたり弱体化させることが出来るかもしれません。
ただ、直接的な効果はあまりないともいわれているため、塩で菌が弱り病気が治るといった考え方にならないよう気を付けましょう。
魚病薬と塩の併用
本来、病気の治療においては観賞魚用の治療薬を使う方が圧倒的に効果的と言えます。
その際にも魚病薬と併用して塩を入れた方が治りやすいと言われています。
その理由の一つが前述の浸透圧調節です。
高塩分濃度で亜硝酸の毒性が下がる?(酸欠防止)
また塩浴のあまり知られていないメリットとして、亜硝酸の毒性が下がるという点があります。
亜硝酸が水中にあると血中のヘモグロビンと結合し赤血球が酸素を運ぶことを邪魔するため酸欠になりやすくなり、人でいう貧血に近いような状態になります。
塩、塩化物(えんかぶつ)イオンが水中に含まれることで、亜硝酸イオンが血中に取り込まれるのを邪魔をしてくれるため結果的に亜硝酸の毒性は下がり、酸欠防止にも役立ちます。
また、メトヘモグロピン血症のような亜硝酸が溜まる病気においては塩を入れることで亜硝酸の吸収が阻害されるので効果があると言えます。
塩を常時入れておけば最強?
こうして知っていくと「塩って最強!」、「メリットばかり」と思いがちです。
人によっては常に塩を入れるという飼育方法で飼育される方もいらっしゃいます。
ここでは塩のデメリットをご紹介します。
塩のデメリット
- 水がアルカリに傾きやすくなる
- 常時塩を入れることで思わぬ事態に!
- 塩分濃度は長期間において安定しない
- 良い細菌にまで影響がある
- そもそも淡水魚を飼育していることを忘れてはならない
※アンモニア毒性↑
※海水由来の病気の発生や病原菌の耐性が上がってしまうことも
※水の蒸発や足し水により塩分濃度が思っている以上に上下する
※硝化バクテリアも細菌の一種=善玉菌にまで影響(悪影響)
実際の塩水浴のやり方
※化学調味料などが含まれているものはNG
また海水魚などで使用される海水の元は海水に近づけるために塩分以外のミネラルなども添加されているため通常の食塩の方が治療には使いやすいです。

塩水浴を行う場合、通常、9割程度の部分換水または全換水を行います。
事前に治療専用の容器を用意しておくと魚病薬や塩水浴による病気の治療もスムーズです。
塩水浴用に準備した容器に水を張り、水温を調整した上で魚たちを移していきます。
※魚たちが調子を崩す主な原因は水質や水温の急変です。治療の際には慎重に水合わせを!
塩水浴の準備が整ったら、塩を入れ、塩分濃度を0.5%程度に調整していきます。
水合わせの上、魚(メダカたち)が入った容器に塩を入れていきます。
塩分濃度は1リットルあたり1gで0.1%です。
0.5%であれば、1リットルあたり5gを入れていきます。(10リットルであれば50g)
この時、一度に沢山入れるのではなく、30分置きに数回に分けて塩を入れていくと魚への負担が少なくより安心です。
また、塩を入れる際には必ずエアレーションなどを使用してください。
澱みをなくしたり、水質面での水の痛みの軽減、また病気の治療には豊富な溶存酸素酸素量も大切になってきます。
.jpeg)
病気の種類や季節に応じて、必要であれば、観賞魚用ヒーターを使い、加温(昇温)する必要があります。
例えば、白点病のように水温を高く保つこと自体が治療に大きく貢献する病気もあります。
.png)
塩水浴の場合も魚病薬による治療の場合も治療期間は概ね1週間程度です。
※魚病薬の場合は薬によって異なるため詳しくは各種説明書をご覧ください。
また、治療中も魚たちからの排泄物や古粘膜の蓄積など水は汚れていくため、1週間程度を目途に水換えが必要です。
症状がまだ完治していない場合は、ステップ1から再度同じことを繰り返していきます。(水換え→水合わせ→塩投入)
メダカ、寄ってくる.png)
治療中は基本的に餌を与える必要はありません。
特にメダカは胃がなく、消化器官が未熟な一面もあるため、体調不良の時は消化不良を起こしやすいです。
ただ、治療が長引きメダカたちが痩せてくる可能性がある場合には餌を与えた方が良い場合もあります。
臨機応変にご対応ください。
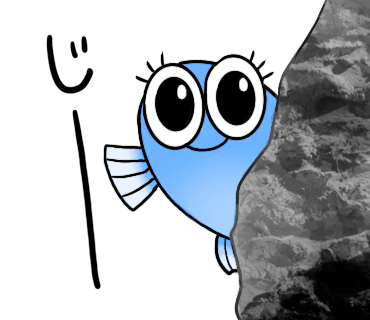

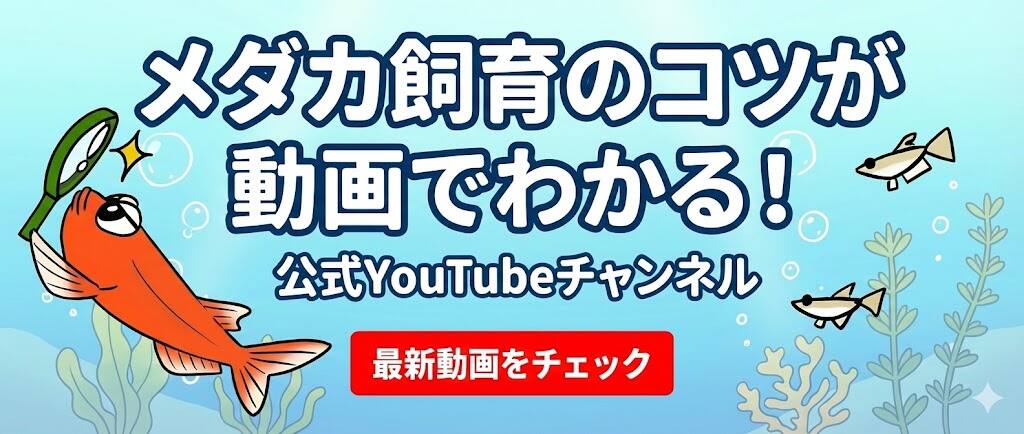
.png)