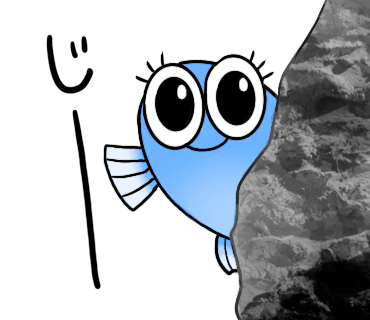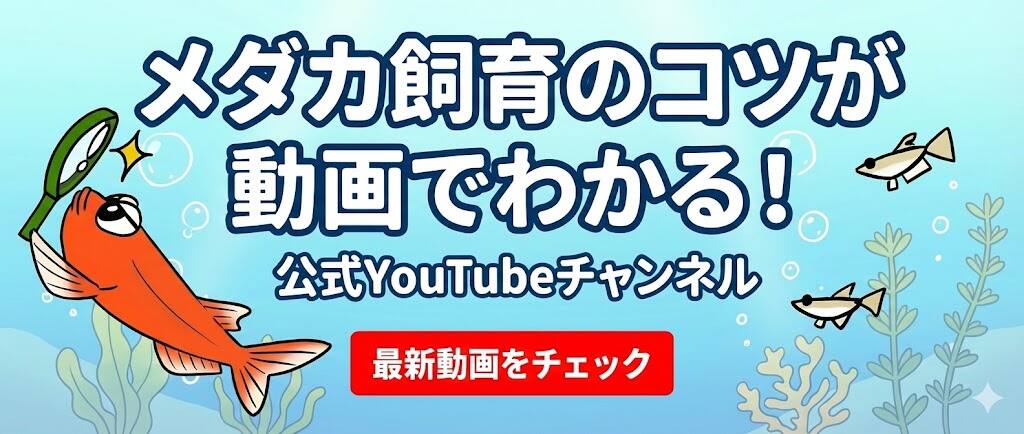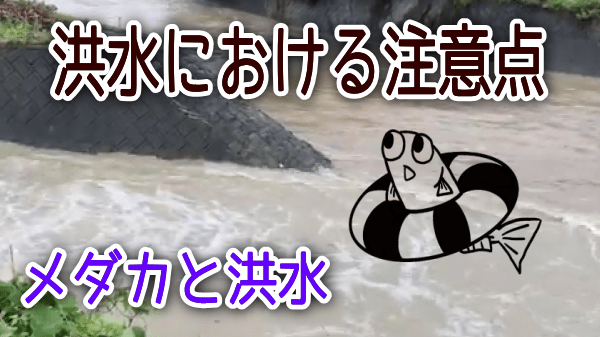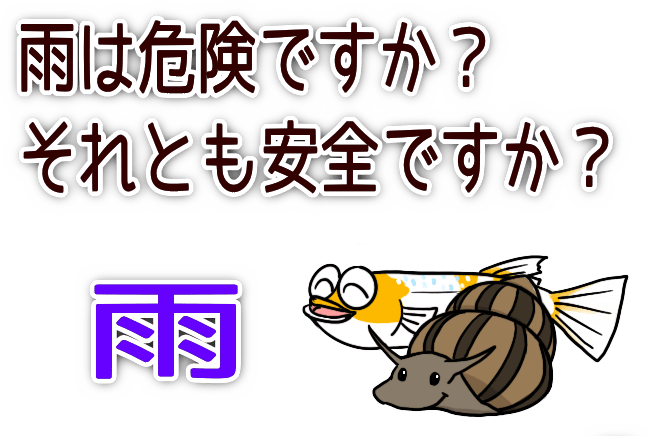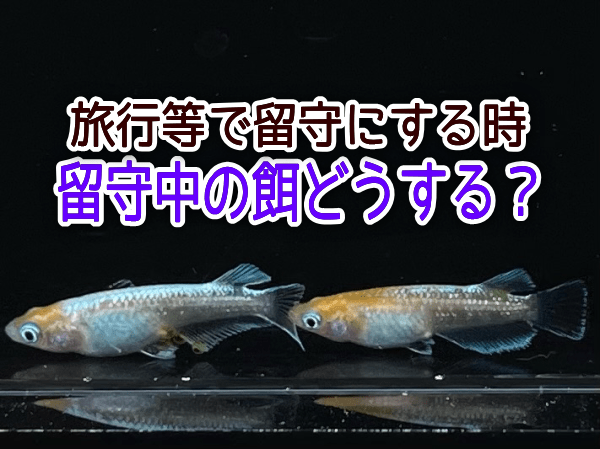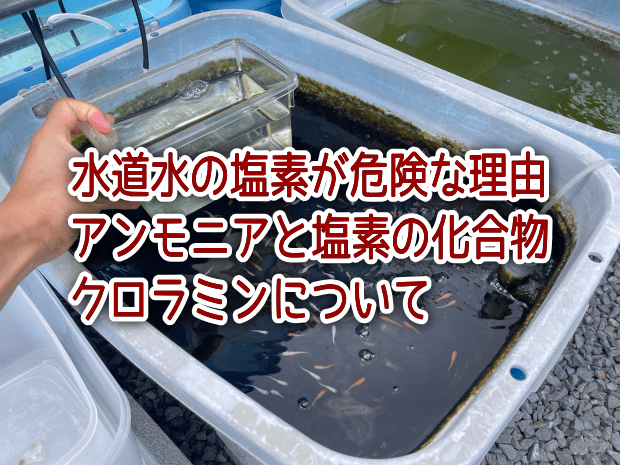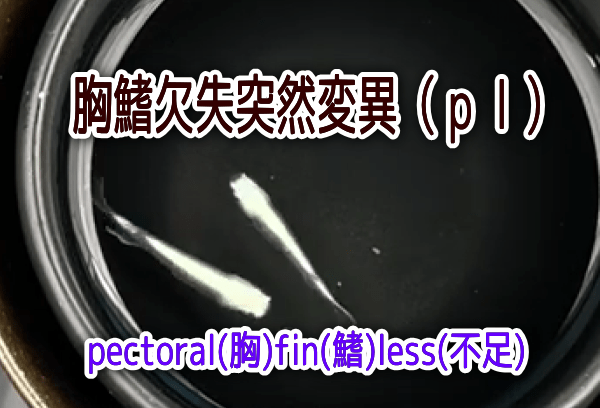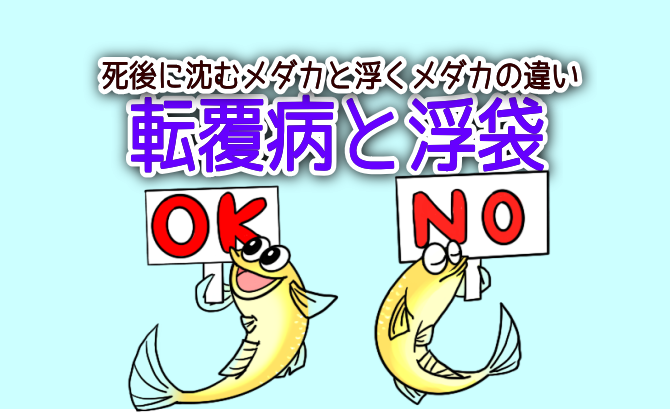発泡スチロールやプラ箱・トロ舟でヒーターの使い方と注意点ほか
【PR】※amazonアソシエイトリンクを使用しています
メダカ飼育ならではの注意点
通常の観賞魚飼育のようにガラス水槽などで観賞魚用ヒーターを使うのであれば通常使用で問題ありません。
ただ、メダカの場合、室内でも発泡スチロール製の容器やプラ箱・トロ舟、タライやNV-BOXなどで飼育することも多いです。
この場合、ヒーターを使う際には注意が必要です。
ヒーターの種類
ヒーターには大きく分けて3種類があります。
- オートヒーター(温度固定式タイプ)
- 温度可変式ヒーター(サーモと一体型タイプ)
- サーモスタットとヒーターがそれぞれ分かれているタイプ
それぞれにメリット・デメリットがあります。
オートヒーター(温度固定式)
.jpg)
オートヒータの場合、大体26℃±で固定されているタイプが多いです。
そのため、少しずつ温度を上げたり下げたりすることができません。
例えば、室内から屋外、または屋外から室内へ移動させる時に少しずつ温度を変化させ魚たちを慣れさせていくということができません。
病気の時に少し温度を上げたい時などにも不向きです。その分、割安な商品も多いです。
※壊れた場合は交換不可の消耗品となります。
サーモ&ヒーター一体型(温度可変式)
.jpg)
このタイプはセンサー部分も一体になっているため非常にコンパクトで使いやすいです。
可変式のため15℃から35℃まで幅広い温度に設定できます。(温度幅はメーカーによって違いあり)
オートヒーターと比べると少し割高ですが、初めての方にもおすすめです。
ただ、オートヒーター同様に一体型のためサーモスタット部分は壊れていなくてもヒーターが壊れてしまうと使えなくなります。
サーモスタット&ヒーター別売りタイプ
.jpg)
サーモスタットとヒーターが分かれている別売りタイプの場合、もしヒーターが壊れても、ヒーター部分だけ交換が可能です。
小型水槽に最適なテトラ (Tetra) ミニヒーター
ヒーターカバーの有無
.jpg)
近年では各種メーカー共にヒーターカバーの装着がマストなっていますが、古いタイプの旧ヒーターだと付いていないものがあります。
使用上の注意点

使うときは必ず、ヒーター部分の近くでエアーレーションするなどして水の流れを作ってください。
.jpeg)
水道水の水が冷たい冬場に水槽を立ち上げた場合、ヒーターが設定温度に達するまで入れっぱなしになります。
この状態で流れも何もないとメダカ容器で使用されているような熱に弱い発泡スチロールやプラスチックは溶けて変形してしまいます。
.jpg)
ヒーターだけでなく、サーモのセンサー部分にも注意が必要です。
センサー部分が水中から飛び出していたり、エアレーションやポンプ等による水流がないとヒーターが入りっぱなしになりやすくなります。
また逆にセンサー部分がヒーターに接触していたりすると、容器の水全体が設定温度に達する前にヒーターが切れてしまいます。
センサーとヒーターの距離は遠過ぎず近過ぎず、ある程度の距離の場所に設置し、水流もある程度必要です。
ヒーターは使い方を間違えると危険です。
説明書などしっかりと読み注意しながらご使用ください。