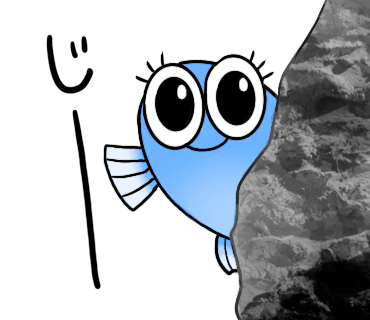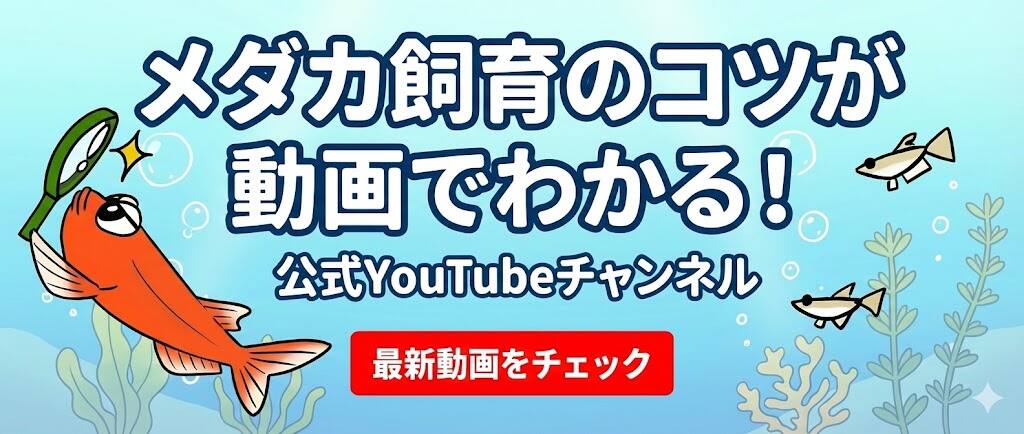ヒカリ体型、リアルロングフィン、アルビノメダカの作り方(品種改良のやり方)
当サイトの記事は全てyoutubeにて映像と共に動画でもご覧いただけます。
非常に分かりやすい動画に仕上がっているため是非、全編(完全版)をYouTubeでもご視聴ください。
メンデルの遺伝の法則について
メンデルの遺伝の法則は遺伝学の父としても知られている生物学者のグレゴール・ヨハン・メンデルが発見した遺伝学を誕生させるきっかけとなった法則です。この法則についてはYouTube(視聴推奨)でも詳しく解説しているため、こちらでは簡易的な説明とさせていただきます。
エンドウを使ったメンデルの実験

メンデルは黄色いさやに対して緑のさやを受粉させた交雑種を作りました。
この時、黄色い豆と緑色の豆のエンドウの間で受粉させた交雑種のF1(子の世代)からは黄色のエンドウ豆だけが実りました。
※交雑によって生じた雑種第1代、子の世代をF1という言い方をします。
※メダカでも掛け合わせの第一世代をF1個体と言ったりします。
メンデルが更に実験を進めていくと子の世代(F1)、孫の世代(F2)、ひ孫の世代(F3)と進めていくと黄色の豆と緑色の豆の両方が実る場合もあれば、黄色の豆だけの場合、逆に緑の豆だけの場合があることに気づきました。
メンデルはこの実験においてエンドウがどれか1つの形質を形作るとき2つの構成要素が関わっているということを発見します。
これが後の「遺伝子」と呼ばれるものになります。
エンドウの実験から分かったこと
他にもメンデルは「優性の法則」「分離の法則」「独立の法則」の3つ法則を導きだしました。
その一つが優性の法則です。
これらの法則が成り立つには遺伝子が対立形質であり、かつ別の染色体上にあることが条件となります。
そのため、現在では例外もたくさんあることが明らかになっており、ごく一般的な形で成り立つのは分離の法則だけであると考える人もいます。メダカの品種改良においても全てをメンデルの法則に当てはめたとしても、その通りになるとは限りません。ただ、メンデルの考えが誤っているわけではないため遺伝の法則を元に改良を進めていくこと自体は間違いではありません。
血液型で考えると分かりやすい?

お母さんががO型で、お父さんがA型の場合=Aの方が優性のため子供はA型が産まれます。
ただ、お母さんがO型なので遺伝子型で見たときにはAOのA形になります。
もし、お母さんもお父さんも遺伝子型がAAのA型であれば、子の血液型もAAのA形になります。
また血液型がAAの人をホモ接合型と言い、AOの人はヘテロ接合型と言います。
いずれの場合もA形であることに違いはないが、遺伝子で見た時に対となる遺伝子が異なります。
メダカに置き換えて遺伝の法則を解説
実際にメンデルの遺伝の法則が改良メダカの品種改良においてどのように遺伝していくのかをご紹介していきます。
潜性遺伝子|アルビノメダカの作り方

※画像がオス同士になっていますが、あくまでも参考画像のため気にせずご覧ください。
普通種にアルビノの個体を掛け合わせても子の世代ではまだアルビノにはなりません。
ただ、F1ではアルビノの遺伝子を対にもった個体のため、孫の世代になると一定数アルビノが生まれてきます。
理論上は普通種が75%生まれ、アルビノ種が25%生まれてきます。
形質的にみれば1:2:1になります。
品種改良の場合は、このF2でアルビノになった個体同士を掛け合わせることでF3雑種第3世代からは全てのメダカがアルビノになりアルビノとしては固定完了です。
不完全優性|光体型メダカの作り方
光体形、ヒカリ体形.jpeg)
ヒカリ体型のメダカは腹側の形質が背中側に反転し相称(そうしょう)するような形質が光体型の特徴です。
厳密に言えば完全な鏡像(きょうぞう)ではないにしろ、腹型が背中側にほぼ反転したような形になるのが光体型です
この光体型を主るDa遺伝子は潜性遺伝子(旧:劣性遺伝子)になります。.jpg)
※厳密にいうと実際には不完全優性といってよく見るとF1でも軟条の数が少し増える形質の一部が現れるのでF1でも光体形を掛け合わせていることが軟条の数からみて取れます。
通常は背ビレの軟条の数は6本程度のところが、光体形の因子を持ったヘテロ個体においては10本前後と増えます。完全な光体形になると尻ビレと軟条の数が同じになります。(18本前後)
棘条と軟条

魚には固い棘条と柔らかい軟条があり、総称して「鰭条」と呼ばれています。
鰭条の間には鰭膜と呼ばれる膜があります。
メダカだと小さ過ぎて分かりづらいですが、少し大きな魚で見てみるとこのような感じになっています。
昔、この話をyoutubeで初めてした時、当時ネット上には情報としてほとんど出ていなかったことからメダカ界のタブーを話したと一部の沼が怒っていました。私からすれば、自分で学んだ知識なので文句を言われる筋合いもない話です。
情報というのは共有するからこそ、新しい物が生まれていくものだと思っています。
メンデルさんが残してくれた遺伝学があるからこそ分かったことでもあります。
光体型に関してはF1でも対立形質の一方が完全におおいきれていないような状態。
不完全優性といえます。
ただ、品種改良を進めていく(光体形を作っていく)上では潜性遺伝子として考えてやっていくと良いでしょう。
先程のアルビノ同様です。
普通体形のメダカに光体型を掛け合わせて出来た子が雑種第1代、F1の個体です。
F2(孫世代)で一部に光体型の個体が生まれてきます。
F2で得られたDa遺伝子を持った光体形メダカ同士でかけ合わせることでF3でほぼ100%光体形になります。
顕性遺伝子|リアルロングフィンの作り方

続いてメダカでは比較的珍しい顕性遺伝子(旧:優性遺伝子)のヒレ変化です。
リアルロングフィンのメダカを作りたい時に普通種にリアルロングフィンを掛け合わせます。
顕性遺伝子なので、雑種第一世代(F1)で全てのメダカがリアルロングフィンになります。
これは血液型がA型同士の親からO型が産まれるように遺伝子型によっては同じA型でもAO型の場合があるためです。
ホモ接合体とヘテロ接合体

リアルロングフィンの場合も同様です。
仮にリアルロングフィンの遺伝子をラージRとし普通種のヒレをスモールrとした時にホモであればRR,ヘテロであればRrいった具合の遺伝子型になり、いずれの個体も見た目上はリアルロングフィンになります。
ただヘテロの場合は対となる対立遺伝子が違っています。ホモではないため一定数は鰭の伸びない個体が出て来るという事になります。
顕性遺伝だからといっても品種改良掛け合わせにおいて100%形質が表に出てくるとは限りません。
RR同士のホモ接合体を持ったリアルロングフィンで掛け合わせた場合のみ理論上、子どもは全て100%リアルロングフィンになります。
ただ、リアルロングフィン自体が頻繁に掛戻しや作り直しがされているため、市場に出回っているRLF(リアルロングフィン)の遺伝子をもった個体の多くはヘテロ接合体のリアルロングフィンである場合も多いと考えられます。
性別を決める遺伝子
他にも性別を決める遺伝子があります。
オスの性染色体がXY、メスの性染色体がXXです。
この場合、概ね通常は雄雌およそ均等に生まれてきます。

例えばメダカは仔魚の頃に性転換する魚として知られていますが生れてきた時にはメス個体、性染色体がXXだった個体が仔魚の頃に性転換して♂の見た目になることがあります。
見た目上はどう見ても♂なので、こちらの個体をオス親として採卵した場合、見た目はオスでも性染色体で見た時にはXXのメスから性転換したオスのため、通常のオス(XY)ではなくXXのオスとなり、親がXX同士になるため子が全てXXのメスになってしまいます。
動画で見る
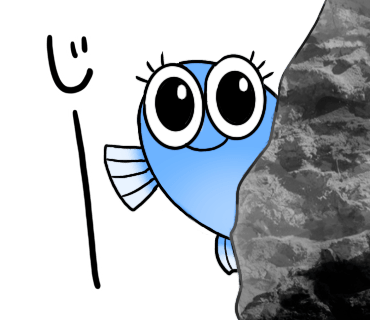
ここではyoutube動画からメンデルの遺伝の法則を元にした品種改良について一部抜粋してお届けしました。
youtubeの動画ではより詳しく他にも色々と解説しています。
是非、ご覧ください。
「媛メダカ めだかの遺伝学」といったプレイリストもあります★